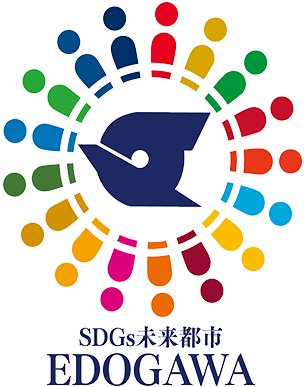江戸川区議会のルール
メール等にて質問の多い江戸川区議会のルールについて掲載します。
会議における議案質疑のルールについて(平成21年9月30日更新)
はじめに、議案の審査について説明いたします。
江戸川区議会では、通常、委員会に付託して委員会で審査を行い、本会議で委員会での審査経過・結果を報告し、本会議での表決の中で議会の意思を決定します。議員数の少ない議会では、通常、委員会に付託しないで、本会議の中での質疑、表決が行われています。また、江戸川区議会でも、内容が軽易で、すでに全会一致で意思が内定している場合には、委員会付託しないで、本会議の中で直ちに、意思決定する場合もあります。
委員会に付託する場合の流れは次のとおりです。
- 提出者の議案説明(本会議)
- 質疑(本会議)
- 委員会付託
- 委員会審査(質疑を含む)
- 表決(委員会)
- 委員長報告(本会議)
- 討論(本会議)
- 表決(本会議)
議会は、合議制の議事機関であり、独任制の執行機関とは性格が異なるところです。合議制の中で、44人の議員は質問や調査を通しながら、自らの意思を決定し、最終的には本会議の中で、議会としての意思を決定しています。その過程では一定のルールに基づいての議会運営が必要です。ルールとは、地方自治法、会議規則、委員会条例等の法令であり、議会内で規定する申し合わせ等のルールをいいます。
次に、議案に対する議員の発言の機会は次の三つがあります。
- 本会議における質疑
- 委員会における審査
- 本会議における討論
本会議における質疑には提出された議案の趣旨説明に対するもの、委員長報告に対するものの2種があります。
問い合わせの多い「議案の趣旨説明に対する質疑」は提出者の趣旨説明があった後、討論、表決に入る前、当該議案の疑問点を質すために行う発言と定義されています。そして、委員会に付託している江戸川区議会の場合には、趣旨説明の後に、その議案の趣旨説明に対する総括的な質疑を行い、付託された委員会で、詳細な質疑を行うのがルールになっています。
それぞれの時点で、最も効果的な質疑を行っているところであり、詳細な質疑を本会議で行うのは的確なことではありません。
なお、委員会の委員でなくとも、付託された委員会で議案について、委員外議員の立場で発言できるルールを定めているところです。
議案審査について(令和6年9月19日更新)
江戸川区議会では、令和6年第2回定例会まで議案は、集中的に審査を行うため総務委員会で議案審査を実施をしていましたが、区議会議員全員が議案審査を直接行うことで、より多様な意見を審査に反映させられることから、令和6年第3回定例会より所管の委員会に付託をすることとなりました。